3年生冬季課外
校内のイチョウの木々の葉もすっかり散って、いよいよ本格的な冬が到来しました。
本校では3年生が12月25日(水)~27日(金)の3日間、冬季課外に取り組んでいます。午前授業で共通テスト対策の演習を行い、生徒の中には午後も教室に残って精一杯励んでいる人たちもいます。
3年生、風邪にもインフルエンザにもコロナにも負けるな。共通テスト本番では万全の状態で実力を出し切ることを祈っています。
【写真下:国語のマーク演習】
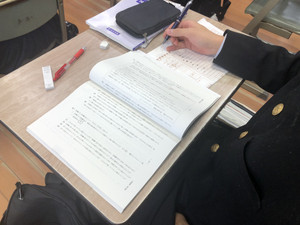
【写真下:西門付近のイチョウの葉は、ちょっと大きい】


甲南高等学校
剛 明 直(ごうめいちょく) 気高く 優しく 健やかに
校内のイチョウの木々の葉もすっかり散って、いよいよ本格的な冬が到来しました。
本校では3年生が12月25日(水)~27日(金)の3日間、冬季課外に取り組んでいます。午前授業で共通テスト対策の演習を行い、生徒の中には午後も教室に残って精一杯励んでいる人たちもいます。
3年生、風邪にもインフルエンザにもコロナにも負けるな。共通テスト本番では万全の状態で実力を出し切ることを祈っています。
【写真下:国語のマーク演習】
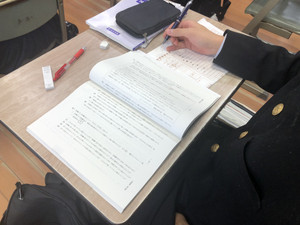
【写真下:西門付近のイチョウの葉は、ちょっと大きい】

9月26日(木)、種子島宇宙センターよりH2Aロケット49号機が打ち上げられ、本校からも白煙が観察できました。

筆者前任地の奄美市では種子島から打ち上げられるロケットの煙は見えませんでした。鹿児島市と南種子町の直線距離は約135㎞。奄美市と南種子町の直線距離は約265㎞。地球の丸さとロケットの軌跡の関係のためでしょうか?
H2Aロケットは次回の50号機を最後に退役し、H3ロケットに移行します。予定は今年度内。有終の美を飾りますように。
北校舎(特に理系側)からは弓道場の向こう側の空を眺めると見つけやすいです。参考までに。
7月26日(金)、今日の午前中も本校内ではクマゼミの大きな声が響いています。
校内の植樹にとまっていたクマゼミのオス・メスを1匹ずつ捕まえましたので(素手で)、雌雄の見分け方について説明します。
【写真下:背面はオス・メス同じように見えます】

まず、セミはオスしか鳴きません。体内の発声膜を振るわせて腹弁から音を出します。セミの腹弁はオスのみが大きく発達しますので、一目で区別できます。特にクマゼミのオスの腹弁はオレンジ色で目立ちますよ。
【写真下:オスの腹弁(オレンジ色の部分)】

【写真下:メスは腹弁が発達しません=鳴かない】

また、メスの尾部は産卵管のため、オスよりも長く尖った形になります。
【写真下:メスの尾部】

他の種類のセミも同じようにこの方法で見分けることができますので、この夏、チェックしてみてください。
7月16日から3年生の廊下にノコギリクワガタのオスを展示しています。
この夏は勉学に専念する3年生に、ほんの少し「童心に帰れる夏」をプレゼント。
【写真下:とある森から甲南高校に到着】

ノコギリクワガタのオスは体のサイズの個体差が特に大きく、大型個体は大アゴ(挟むところ)が大歯型に、中型個体は中歯型に、小型個体に小歯型(通称チビノコ)になります。
中歯型や小歯型を展示すると、よく「先生、このクワガタは今から大きくなるんですか?」と聞かれますが、蛹から羽化したクワガタの成虫は、それ以上大きくなることはありません。
温度や栄養状態等、様々な要因が指摘されていますが、端的に言うと「幼虫時代に大きく育ったものが大歯型になれる」。幼虫時代に十分に生育することが大切なのです。
生徒の皆さん・中学生の皆さん、よい環境でしっかり栄養を蓄えて(比喩的)、大型個体になりましょうね(これも比喩的)。
【写真下:クワガタと戯れる生徒】


7月11日(木)昼間の学食の前で、外傷はないのに息絶えているニホントカゲ(爬虫類)を見つけました。
ニホントカゲの幼体の尻尾は明るい青色で金属光沢があります。この個体はだいぶ大きいですが、まだ尻尾に青みが残っているので、成体になる一歩手前といったところでしょうか。
生きている個体を捕まえて紹介したいところですが、昼食時間の生徒の前で追いかけ回すのは少々勇気が必要です。
【写真下 ニホントカゲ全身と青みがかった尻尾】


江戸時代後期に薩摩藩が編纂した『三国名勝図会(ずえ)』。
領内の名所・地誌を記す書物で全60巻。特に寺社については由緒・外観まで詳細に記されています。
では、図会に掲載されている歴史ある神社で、本校と関連の深い神社を紹介します。
荒田八幡宮: 大隅正八幡宮(現在の鹿児島神宮)の荘園、荒田荘に建立された神社。現在でも,かつての荒田荘(神領)の領域を示す東西南北4つの祠があり、随神(ずいじん/ずいしん)が祀られています。
「随神」とは随身(貴人を警護する官人)の姿をした、神を守る存在で、北の随神の祠は甲南高校の南東の角にあるのですよ。テニスコートのそばです。気づいていますか? 本校も守護していただいているような気もします。
残り3つの祠も公的な場所に現存しています。探してみてください。地図にマークすると,かつての荒田荘の広さがイメージできます。
写真下:北随神祠


5月27日(月)は3年生の放課後自習の初日になるはずでしたが大雨予報で延期となりました。本格的な梅雨が来る前に、雨に親しむための記事をひとつ。
「雨:あめ」の語源は諸説ありますが、一説には「天:あめ」と同義だとか。その説によると、空の上が「あめ」で、そこから水が落ちてくることを「あめ」が降る、というそうです。すると、中国から漢字が流入した際に、意味によって「天」と「雨」に書き分けられたということになります。
日本は四季の変化が豊かで稲作文化圏です。そのため、雨に関する語彙が豊富です。霧雨・小糠雨・小雨・時雨・村雨・五月雨・梅雨…など。
豊かな語彙はその文化圏の特徴を表します。氷雪に関する語彙が豊かなところもあれば、ラクダに関する語彙が豊かなところもあります。
それぞれの文化圏が言葉で外界をどのように切り取ったのか? この問いも科学に含まれないでしょうか。
写真下:5月31日(金) 雨の校内の風景



本校西側のアリーナの陰にはビワの木があり、今年も果実が実っています。植物の枇杷(ビワ)の名称は、楽器の琵琶の胴と形が似ていることから付けられました。
もともと楽器の琵琶も木製ということで「枇杷」と表記されていて、後に琴(弦楽器)の一種であるため「琵琶」と表記されるようになったと言われています。
一年中店舗に並ぶ果物は増えてきましたが、ビワはまだまだ季節物。おいしそうですね。


桜の季節は終わろうとしていますが、本校内には他にも多くの花があり、華やいだ季節は続いています。
葉桜になりにけり。

藤棚のフジも咲いています。

玄関のガクアジサイ。花びらに見える部分は「萼片(がくへん)」と言います。

玄関のナデシコ。旧制二高女のシンボルフラワー。本校の校章にも用いられています。

事務室内にクリスマスローズ。これも萼片が花びらのように見える花です。

新2・3年生の皆さんは部活動や自学で登校している人も多いと思いますが、見頃を迎えている本校の桜は眺めましたか。
正門の桜を校舎2階から

本校敷地の北西角の桜を校舎2階から

来週8日(月)は始業式です。校門を通る際には桜を一目眺めて、気持ちも新たに校舎に向かいましょう。
生徒の皆さんにとって良い1年となることを祈ります。